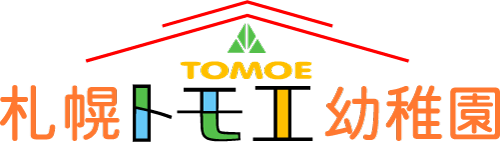①自他の“主体”を尊重し合える関係づくりの場
・主体としての自分
トモエでは、自分で感じ、考え、行動することを大切にし、主体としての自分を実感できるようにしています。その積み重ねによって心地よい自己充実感が生まれ、自己肯定感へとつながり、自分自身を信じて前向きに生きる力が育まれることを重視しています。
・真の自己愛
トモエでは、自己肯定感を育む経験を重ねると同時に、時には自分の弱さや失敗、未熟さといった自己否定的な側面も受け入れることを大切にしています。こうした両面の経験を通じて、子どもたちは自分自身を深く理解し、ありのままの自分を愛する「真の自己愛」を育んでいきます。
・他者の尊重
トモエでは、主体としての他者を尊重することを大切にしています。子どもも大人も互いの考えや感じ方を受け入れ、寛容な心で見守り、相手の成長や変化を信じて待つ姿勢を育みます。こうした関わりを通じて、互いに期待し合いながら信頼関係を築き、共に成長する場を目指しています。
②(言語的・非言語的)コミュニケーション能力の基礎を胎・乳幼児期から養い向上させる場
・胎児と母胎のコミュニケーション
胎児と母胎は、血液や栄養のやり取りを通じて深く結びついています。胎児が成長する力に母胎が応え、促すことで、両者の間には複雑なネットワークが生まれます。この関係性は、言葉を超えた最も原初的なコミュニケーションの形であり、人間のつながりの基盤となっています。
・母子間の情緒的な交流
乳幼児と母親との関係は、主に母子間での世話をする・されるという相互作用を通じて築かれます。この関係性では、互いの感受性や応答性が重要な役割を果たし、日々のやりとりの中で情緒的な交流が深まります。母親と乳幼児は、時に主となり時に客となる立場を繰り返しながら、情緒的な共鳴を経験します。こうした体験の積み重ねが、子どもにとってのコミュニケーション能力の基盤となり、他者との関係を築く力や自己表現の力を育む土台となります。このような初期の親子関係は、子どもの社会性や情緒の発達にとって極めて重要な役割を担っています。
・共感的・非共感的コミュニケーション
トモエでは、子どもたちが日々の生活の中で「共感的反応のコミュニケーション」と「非共感的反応のコミュニケーション」の両方を経験することを重視しています。共感的反応のコミュニケーションとは、積極的な身振り手振りや表情、会話の継続や盛り上がりなど、相手と心地よく関わるやりとりを指します。一方、非共感的反応のコミュニケーションは、消極的な態度や引きつった表情、目をそらす、会話の中断や拒否など、心地悪さを感じるやりとりです。子どもたちは、こうした両方のコミュニケーションを体験することで、他者との関わり方や自分の気持ちの伝え方、相手の反応への気づきを深めていきます。特に、共感的なやりとりが多い環境は、子どもたちの自己肯定感や信頼関係の形成、豊かな人間関係の基盤づくりに大きく寄与します。様々な経験を通して、子どもたちは豊かなコミュニケーション能力を育んでいきます。
③素直に表現する乳幼児から学び、大人も素直に表現することで、互いに理解が深められる場
・ありのままの表現
乳幼児は、正直な情緒的反応や自己主張、自己防衛といった即自的な反応を通して、ありのままの自分を素直に表現します。この素直な自己表現は、自分自身への誠実さだけでなく、相手のありのままを受け入れる寛容さとも結びついています。トモエ(コミュニティ)幼稚園では、子どもたちが喜怒哀楽を率直に表現できる環境を大切にし、その時々の人間性を尊重しています。こうした素直な感情表現は、周囲の大人や仲間たちとの共感的・受容的な関係の中で理解し合う土台となります。大人もまた、乳幼児の姿から学び、自分の感情を抑え込まずに素直に表現することの大切さを実感します。互いにありのままを受け入れ合うことで、より深い理解と信頼関係が育まれ、温かなコミュニティが形成されていきます。このような環境の中で、子どもも大人も自分らしく成長し、豊かな人間関係を築くことができるのです。
・心の解放と癒し
大人は日常生活の中で、時に説明しがたい大きな情緒的苦痛を感じることがあります。その根底には、幼少期から無意識のうちに感情を抑圧し続けてきた経験が影響している場合が少なくありません。自分の本当の気持ちや感情を押し殺してきたことに気づくことは、自己理解の第一歩となります。そして、その気づきが自己変革への道を開きます。トモエ(コミュニティ)幼稚園では、大人自身が自らの感情に向き合い、過去の抑圧に気づき、受け入れることを大切にしています。自分の感情を素直に認め、表現することで、心の解放や癒しが生まれ、より豊かな人間関係や自己成長へとつながっていきます。このような気づきと変化は、子どもたちの成長にも良い影響を与えます。