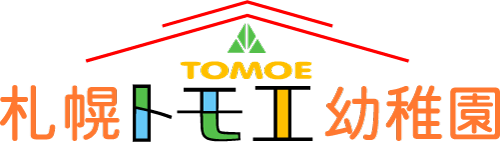「心の広い人とは?」 & 「あなたの将来の夢は?」
米澤正人
〈心の広い人とは〉
先日、ある卒園家族のお母さんが久しぶりに顔を見せてくれました。軽く挨拶を交わした後、私は長男のトモくん(仮名)が元気にやっているか尋ねました。トモくんは、見た目は落ち着きがあり人当たりも穏やかな感じですが、中学を卒業したころだったでしょうか、自転車で日本のあちこちを一人で回る旅をしたいと実行に移すバイタリティの持ち主でした。彼は高校を卒業するころになって「大学に行って勉強したい」と思い始めたようで、いま予備校に通いだしたということでした。高校生活を経て、新しい目標に向かい自らの道を選ぶトモくん。お母さんもお父さんも、進路についてはあくまで本人に任せてきたそうです。その姿勢もまた、彼の芯のある成長を支えてきたのでしょう。
彼のことを思い出すと、どうしても忘れられないエピソードがあります。まだ彼が小学校6年生だったころ、お母さんから聞いたある出来事です。当時、道徳の授業で「心の広い人とはどんな人か?」というテーマが取り上げられ、生徒たちはその感想を「学習ノート」というプリントに綴ったそうです。そして返却されたそのプリントを見たお母さんがびっくりして私に教えてくれたのでした。自分が思う「心の広い人とは」どんな人かを書く欄、そこにはこう書いてあったといいます。
『いろいろな世界を知っていて、その人に合った自分の思いを言ってくれる人』
それを聞いて私も驚きました。あまりにも本質を突いた言葉だったからです。
「いろいろな世界を知っていて」とは、単に多くの場所に行ったことがあるという意味ではないのでしょう。それは、文化や習慣、宗教、言葉、価値観といった、人々の生き方や考え方の多様性に触れ、理解する力のことを指しているのだと思います。価値観の違いを知り、それを受け入れようとする姿勢。自分とは異なる背景を持つ人に対して、偏見なく接することができる人。それが彼にとっての「心の広い人」だったのだと思いました。
とかく人は、自分と考えが合う人、価値観が同じ人(同じとまではいかなくとも似た人)と付き合いを深めていきます。それはそれで必要なことだし、それなしでは生きるということに疲れてしまいます。しかし同時に、それだけだと人生は味気なくつまらないということ、また自分の人間としての成長が滞ってしまうということ、つまり心の広い人にはなれないということは、ある程度年を重ねてくるとわかってくることです。しかし彼は、12歳でそれを感じて(知って)いたのでした。
そしてさらに驚いたのが、続く一文でした。
「その人に合った自分の思いを言ってくれる人」
この言葉には、大人でさえ言葉を詰まらせるような深い洞察があると感じたのです。
「その人に合った」とはどういう意味でしょうか。これは、ただ優しい言葉をかけるという意味ではないのでしょう。相手の性格や状態、心のありようを見つめ、その人にとって一番伝わりやすく、受け入れられるかたちで、自分の思いを表現するということです。単に相手の機嫌を取ることではなく、相手の性格や気持ち、タイミングを思いやった上で、それでもなお自分の考えや感じたことを伝える。優しさだけでもなく、正直さだけでもなく、そこには誠実な「配慮」がある。思いをただ投げつけるのではなく、受け取ってもらえる形で届けること――それこそが、コミュニケーションの核心ではないでしょうか。
しかし、それは簡単なことではありません。大人ですら、自分の言いたいことばかりをぶつけてしまい、相手の気持ちに配慮できずに後悔することがあります。言葉とは刃にもなり得るからこそ、伝え方に心を注ぐ。それを12歳の少年がすでに感じ取っていたということ、その繊細さに、彼の人としての成熟を感じ、私は言葉を失いそうになったのでした。
〈あなたの将来の夢は〉
お母さんとの会話は、自然とトモくんの弟、ケンちゃん(仮名)の話題へと移っていきました。今、彼は小学6年生。新学期が始まって間もない頃、学校で「自己紹介」のプリントに書いた内容が、またお母さんを驚かせたといいます。
返却されたプリントには、自分の好きな遊びは何かなどを書くいくつかの項目がありましたが、最後に「将来の夢」という項目があって、そこは先生の説明では将来自分が就きたい職業を書く欄であったといいます。そこに彼は悩んだ挙句、
「一人一人を大切にできる大人」
と書いたというのです。それを聞いて、一瞬言葉を失い、胸が熱くなっている自分がいました。
お母さんが、「なぜやってみたい職業を書かなかったの?」と尋ねたところ、ケンちゃんはこう答えたそうです。
「やってみたい仕事は、今までも変わってきたし、これからも変わると思うから」
なんというまっすぐな答えでしょう。そこには彼の、将来も変わらない、変えたくない夢が描かれていたのです。自分がどんな職業に就きたいかではなく、どんな人間でありたいか。それを最優先に考えるその姿勢に、まさに「人としての核」があると感じました。多くの大人が、職業や肩書に「夢」を重ねます。でも彼にとっての夢は、外側のかたちではなく、「人としてのあり方」にあったのです。
お母さんは、「家でそんな話はしていないんだけど」と言っていました。つまり、言葉として誰かに教えられたわけではなく、彼が日常の中で、周囲の人たちの姿を見て、自分で感じ取り、心の中に芽生えさせた思いなのでしょう。
かつての日本の家庭では、「礼儀を大切に」とか「人様に迷惑をかけてはいけない」、「正直でいなさい」といった言葉が、親から子へと自然に語られていました。しかし、時代も変わりそうしたことに含まれる自己抑制の側面に精神的負担が相対的に大きくなったからでしょうか、それらの言葉は死語になりつつあると思います。ケンちゃんの家で話題になっていないことが彼の表現として現れたのは、ひょっとして、親を中心に周りの人たちを見て彼がそう感じていたということかもしれません。そういう意味では、昔の人の言葉も、実際の言葉よりも大人たちの生きざま、背中で語ることを感じていたことが大きかったのかもしれません。
〈トモエコミュニティで育つということ〉
話の最後に、お母さんがしみじみとこう言いました。
「これは、トモエに小さい時から通って、たくさんの人とかかわってきたことが大きいのだと思います」
私はその言葉に、静かな確信と感謝の気持ちを抱きました。子どもが親の影響を最も強く受けて育つことは言うまでもありません。そして、トモエコミュニティはそこに深く関与していると思います。
トモエでは赤ちゃんからお年寄りまで集い、各々が自分のペースで自分の相性の合う人、大好きになった人と関係を深め、またその幅を広げていけます。そこでは様々な人との関係が縦横無尽に築かれ、一緒に怒ったり泣いたり笑ったり、子どもとか大人とか関係なく誰かの言動に感謝したり感動したり、また癒されて元気になったりということが起きています。そこでの「心地よい関係」「信頼し合える関係」は、人を安全と安心のなかで成長させる舞台となっています。トモくんとケンちゃんのお母さんとて、在園時代は悩みや苦しさを抱えていたときにいろんな人に支えられてもいました。トモエコミュニティには、「人間としてどうあるべきか」という問いに対する無言の答えが、日々の暮らしの中に溶け込んでいます。子どもは見ているし、感じています。人間にとって大切なことは何かということを。
子どもにとっても大人にとっても、周りの人との関係がいつも良好とは限りません。イライラするとき、悲しくつらくなるときなど、自分にとっての不快な体験もしています。実際、今この瞬間にもそうした苦しさを感じてつらい思いをしている人だっているはずです。しかし、ひょっとするとそうしたことよりも数は少ないかもしれないけれど、身も震えるような心地よさや感動をいろんな人から、また様々な場面を通して感じ取っている(感じ取ってきた)のではないでしょうか。
特に子どもたちは、吸収するのにうってつけのこの時期に、人間としての在り方・・・人間にとっての大切なこととは何かというエッセンスを、様々な人たちから様々な形で受け取っています。そしてそれらを自分の力で構築しているのだと思います。大人にとっても同じことです。大人は、自分の適応スタイルを積み上げてきた歴史があるので時間はかかるかもしれませんが、この舞台で様々な体験を通して、自分の育て直しということを含めて、自らを変化成長させていけます。私自身、そうした人たちをたくさん見てきたし、そこから人間に対する希望を膨らませてきた部分があります。
以上のように、子どもたちの心の中にある言葉や思いには、それを知って私たち大人がハッとさせられることがたくさんあります。私自身そういうことに何度も出合ってきました。その都度考えさせられるのは、子どもたちは「本質」を見抜く目を持ち、その目で私たち大人の後ろ姿を見ているということです。それは私自身の生き方への戒めになる一方、私たち大人がどんな姿勢で生きているのかが、彼らにとっての「道しるべ」になっているとしたら、こんなに嬉しいことはありません。
トモくんとケンちゃん・・・彼らの中に確かに育まれている人としての感性と、彼らを支えてきた家族、特にお母さんの存在。そして、そのお母さんを支えてきたトモエという場。みんなが集い、みんなで創っているこの環境。私はその一員でいられることを、心から誇りに思います。彼らの姿は、まさにこのトモエコミュニティで育まれる人々の営みの尊さを、そして未来への希望を、私たちに静かに、そして力強く伝えてくれています。
園内便り「トモエ便りNo.5」(2025年6月2日発行より)