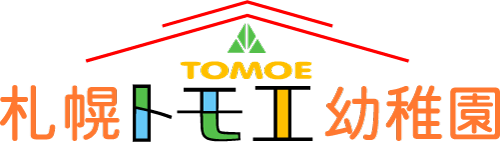「主体」とは何か – 人間の尊厳と幸福の創造に向けて
木村 仁
はじめに
私は長年、札幌トモエ幼稚園の園長として、乳幼児と家族の皆様と共に歩んできました。その中で常に私の心を占めてきたのは、「主体」という概念です。この「主体」とは何か。それは単なる辞書的な意味合いを超え、人間の存在意義、幸福、そして平和の創造に深く結びつく、生涯にわたる探求と実践の核心に位置するものだと確信しています。それは、人間観察(自己観察)と胎児・乳幼児と母の観察を核としています。母とは、命を宿し育む存在として・・・。
「主体」の本質 – 唯一無二の存在として
私が考える「主体」とは、その人しか持っていない独自の「命」や「魂」から発生する言動です。これは認識し、行為し、評価する「我」を指し、特に「個人性、実践性、身体性」を強調する言葉です。
「私という人間は、私のみ。独自の命。人と比較できない存在」 – この言葉に、私の「主体」理解のすべてが込められています。人間はそれぞれ異なる遺伝子を持ち、個性や気質も異なる唯一無二の存在です。他者と比較することは「悲劇の根源」となり得るものです。この唯一無二の「主体」を自覚し、そのありのままを受け入れることが、人生における真の理解と幸福への第一歩なのです。
私はこの「主体」の概念を「人間の特殊相対性体系・基礎編」として考察を進めています。人間個々が自分を核として、すべての事象と相対的に感じ、考え、表現しているという独自の視点です。この「主体」は、過去や現在だけで評価されるべきものではなく、常に未来に向かって成長し、変化し、進化し続ける存在〈私〉なのです。
主体形成の起源 – 胎児期・乳幼児期の神秘
「主体」の形成と発達は、人間の誕生の瞬間から、特に胎児期・乳幼児期にその根幹が築かれます。
(参考資料 NHKスペシャル 人体Ⅲ 命・細胞)
生命誕生という神秘的ドラマ
人間の命は、男女の信頼関係と肌の触れ合いから始まり、母親の子宮の中で神秘的なドラマを経て育まれます。この胎児期の経験が、その後の人生における個性や気質の基礎を築く上で極めて重要です。母親が胎児の命の営みを10ヶ月間体験し、命を育む存在であること自体が、「偉大」であり「壮大」なことなのです。命の存在は、母を抜きにしては・・・。
母親からの「信頼される喜び」~愛着と脳の記憶の重要性
生まれたばかりの命は、親、特に母親からの「信頼される喜び」を、目や肌、五感を通して日々感じ取り、「生きる喜び」を身につけていきます。この「信頼される喜び」こそが、自己肯定感(自分を信頼する感覚)の基礎となります。自分を信頼できる人は、他者をも信頼できる人間になるのです。
この信頼の基盤が希薄な環境で育った場合、深い心の傷を負い、自己を見失う可能性が高くなります。そのため、母親の精神的な安定と、家庭における信頼関係の構築が、子どもの健全な「主体」形成に不可欠なのです。
乳幼児の持つ「超能力」
私は、乳幼児が「人間の中で一番感性が研ぎ澄まされた時期」にあり、「球体のような感性で、あらゆるものを感じ取る能力を持っている」と確信しています。特に、生後間もない乳児の目は「超能力」を持つほどに鋭く、大人の心や感情、誠意の度合いを瞬時に感じ取る能力があります。
- ある文献では、「幼子を受け入れるものは、神を受け入れたのと同じだ」とある。乳幼児の不思議な世界を55年間観察・探求中。
乳児は、目の前に現れる大人の目を長く見つめることで、その人が自分をどのように見ているか、どれだけ敬意を払っているかを感じ取っています。この時期の乳幼児は、大人が創る生活環境を「100パーセント受容」して生きる存在であり、彼らが持つ「ありのままを受け入れる能力」は、人間の本質そのものです。
ポール・トゥルニエ博士が述べたように、大人から「敬意を払われる度合いに応じて自分の人格を意識し、自分の人間としての尊厳を自覚して自分自身を尊重するようになる」のです。これは主体の認識の核となるものであり、良心の形成と道徳教育や性教育の基礎となります。
「仮面」と「本音」の問題
乳幼児期における「主体」の形成において、素直さや本音での自己表現は不可欠な要素です。乳幼児は本能的に自分と向き合い、素直に表現することで、自分の言動が他者にとってどうであったかを判断し、自己調整する能力を養います。
しかし、現代社会では、大人が「教育やしつけ」の名のもとに子どもに強制したり、本音を出すことを抑圧したりすることで、子どもは仮面をかぶり、真の自己表現ができなくなる傾向があります。仮面をかぶり続けることは「自分をごまかす」ことに繋がり、最終的には「本当の自分を失うことで、孤独な人生を歩む」(主体を見失う)ことになりかねません。
真の素直さとは、他者への都合の良い対応ではなく、自分自身に正直に応答することです。これができなければ「自分を知る」ことはできないのです。
主体性確立への実践的道筋
「主体」の確立と成長は、生涯にわたる意識的な努力と実践によって実現されます。
「自分と向き合う」生活の根本
「主体的に生きる」ことの根本は、「自分自身と日々向き合い続けること」にあります。これは、自分自身の心、魂、良心といった内なる存在と「対話」することであり、「まだ知らない自分と出会う」ための道です。この「自分と向き合う」旅は苦悩を伴いますが、同時に不思議な世界の新たな発見と「生きる喜び(無尽蔵)」をもたらします。
「人間相対性理論」による自己理解
私は自身の哲学を「人間の特殊相対性体系・基礎編」と呼んでいます。これは、自分を核としてすべての事象を相対的に感じ、考え、表現するという人間存在のあり方を説くものです。
この理論は、自分自身を過小評価したり、誇張しすぎたりするのではなく、自分の「物差し」(胎児期・乳幼児期の脳環境の記憶に由来する個人的な基準)を柔軟に拡大し、ありのままの自分と他者(私と同じ存在の人間)を受け入れる努力をすることを含みます。人生における喜びや苦悩、長所や短所といった「マイナス」と「プラス」の両面を直視し、それらを総合的に受け入れることで、心のバランスを保ち、より豊かな(心身のバランスをとれる)人生を歩むことができるのです。
「良心との対話」の重要性
「主体」の確立において、「良心」は極めて重要な役割を担っています。良心は、人間の行動の真意を推し量る能力として生まれつき備わっており、魂や心、身体のバランスを整える機能を持ちます。
良心との対話が良好であれば、人は心のバランスがとれて素直に表現できるようになり、内面から喜びが湧き上がります。逆に、良心との対話が少ないと、心が不安定になり、自分を見失うことに繋がりかねません。良心と誠実に対話することで、人間と神の神秘を(日々新しい発見の未来の)体験ができるのです。
特性の発見と可能性への信頼
私は、生きる上で最も大切なこととして三つのテーマを掲げています。「自分と向き合うこと」「自分の特性を日々発見し続けること」「自分の可能性を日々信じ続けること」です。
自分の特性(個性や長所・短所)は、日々の生活体験や人との関わりの中で発見され、これによって新たな自己の発見と、自分を信じるきっかけが増大します。そして、人間は「無限の可能性」を秘めた存在であり、その可能性を信じ続けることで、未だ見ぬ「新しい自分」や「新しい世界」に出会うことができるのです。
この自己の可能性への期待こそが、人生を「楽しく、おもしろい」ものにし、未来を創造するエネルギーとなります。人間は、無尽蔵の世界を持っているのです。
「自由」の創造的力
「自由」は、主体的な自己表現を可能にし、それを通じて自己理解と人間理解を深める重要な要素です。乳幼児期に自由に自己表現する機会が与えられることで、子どもたちは自らの言動を客観的に見つめ、他者を鏡として自己を調整する力を養います。
この自由な表現から生まれる「想像力」と「創造性」は、ミヒャエル・エンデが述べたように、人間の「永遠の子どもらしさ」そのものであり、真の人間らしさを構成する能力です。胎・乳幼児と母を核とした家族に学びながら、私はこの創造性を最大限に引き出す環境をトモエ幼稚園で提供しようと試みています。
「待つ」愛と「許す」心
「主体」の成長を見守る上で、「待つ」という行為は「愛」です。特に、乳幼児の成長は待つことが不可欠であり、性急に「正解」を求める現代社会の風潮に一石を投じたいと思います。
また、他者、そして自己の不完全さや失敗を「あるがままに受け入れ」「許す」ことの重要性も忘れてはなりません。特に、大きな心の傷を負った母親であっても、自分の「あるがままを受け入れ許せる心」が人間には必要なのです。※(参考資料セビリヤの理髪師より 子どもに理想を押し付ける大人)400年前
トモエの実践 – 主体を育む生活環境
トモエ幼稚園の生活環境は、私の「主体」哲学の実践の場として創造されてきました。
「創造家族」という共同体
トモエは、単なる教育機関ではなく、「家族的な生活環境(共生の場)」を基盤とした「社会共同体」として機能しています。ここでは、在園家族だけでなく卒園家族も参加し、互いに支え合い、助け合い、個々の才能を認め合う環境(子どもと共に大人も育つ場・共育)が創られています。
この共同体において、人々は「自分と人を好きになる」ことを学び、「心が通い合う心地よさ」を体験することで、幸福の基盤が築かれます。
親と大人の自己変革
トモエでは、大人が「自分を見つめ、自己を修正し成長していく」ための環境が提供されています。特に母親は、乳幼児との関わりを通して、自身の乳幼児期の経験や愛着のあり方と向き合い、自己理解を深め、主体の認識を育む機会を得ます。
大人が素直に感情を表現し、子どもと本音で関わり合うことで、互いの理解が深まり、真の人間関係が築かれます。また、男性は女性を、女性は男性を「理解しようと努力する」ことが、温かい心の交流を生む上で不可欠です。子どもは、大人の愛(理解と努力の)型を、主体(命・魂・良心)全体で感じ取っています。大人も、子ども時代を思い起こしましょう。
自然との調和と五感の育成
トモエは、子どもも大人も「大自然の中で五感を球体的に刺激される生活」を送ることを重視しています。自然は「人間の本能や資質をよみ返らせてくれる」存在であり、「自然に勝る教師なし」です。
砂・泥遊びや川遊びなどを通して、子どもたちは自らの身体感覚(機敏性、敏捷性など)を養い、危険を察知し、安全を学ぶ経験を積むことで、人間本来の能力や感性が育まれます。これは、現代社会における「心の砂漠化」や「人間性の喪失」に対する重要な対抗策と考えています。大自然の中で、毎日生活しています。
「人間科学の基礎」としての探求
私の長年の実践と研究は、「人間科学の基礎」という独自の探求に集約されます。これは、生命の誕生から始まり、胎児・乳幼児と母親の関係性を核とした、人間の心、魂、良心、身体、そして夫婦・親子・家族・社会といったあらゆる側面を「総合的」かつ「球体的」に考察するものです。
この人間理解の探求こそが、幸福で平和な社会を創造するための不可欠な基盤であると確信しています。
主体性と幸福・平和の創造
私の「主体」に関する思想は、最終的に個々人の幸福と、ひいては社会全体の平和の創造へと繋がっています。
幸福の原点 – 心の交流
幸福の根源は、「自分自身と心が通い合う対話」にあり、さらに「自分と愛する人、そして多くの人との心地よい心の交流」にあります。この心の交流を通じて、人は「生きる喜び」や「生きるエネルギー」を感じ、幸福を日々「創造」していくことができるのです。
主体理解から他者理解へ
「自分を好きになること」は、幸福の最も基本的な鍵であり、それができれば「人も好きになれる」のです。主体理解は、他者を理解し、受け入れ、優しさや思いやりを持って接するための基盤となります。他者の「あるがままを受け入れる」姿勢は、差別のない社会を築き、共生を可能にします。
(参考資料 自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ その定義・法則の観察と探求)
次世代への遺産
私は、大人たちが次世代に「生きる意味」や「幸せを創造する力」を遺産として残すことの重要性を強く感じています。これは、単に物質的な豊かさではなく、心を豊かにする生き方、つまり「幼い時代の愛情に満たされた陽だまりのような日々」や「心が通い合う心の交流の喜び」を継承していくことです。
私の実践が未来の子どもたちの幸せな生活環境に繋がることを願って、生涯をかけて観察・探求と創造を続けています。
終生にわたる探求の道
私の「主体」に関する考え方は、私自身の波乱に満ちた人生と、生涯にわたる絶え間ない観察・探求によって形成されてきました。
未完成な存在の無限性
私は、人間は「完璧な人間にはなれない」「永遠に未完成な存在」であると同時に、「無限の可能性に満ち溢れている存在」であると考えています。この未完成さこそが、生涯にわたる自己探求と成長の原動力となるのです。
苦悩との共生と進化
私は、自身の人生を「孤独と苦悩」の連続と感じながらも、それらと「仲良くしながら」、あるいは「自分の弱さと戦いながら」、日々進化し続けることを選び取ってきました。苦悩は時に深いものですが、それを乗り越えることで「新しい自分」に出会い、喜びや生きる力が湧き、人間としての「進化」を体験できるのです。
知的好奇心の永続性
私は、15歳頃から「人間とは何か」「生きる意味とは何か」「私は誰」といった根源的な問いを抱き、その探求を生涯にわたる自身の使命としてきました。
「私には特殊な才能はありません。ただ、熱狂的な好奇心があるだけです」というアインシュタインの言葉に、私は自身の生き様を重ねています。自分について、人間について「分からないことを知りたいと求め続ける」ことの重要性を、私は身をもって感じています。
この「知的好奇心」が、人間が生きている限り「神秘と不思議」に満ちた世界・無尽蔵な可能性を秘めた人間を発見し続ける原動力となり、人生を豊かにするのです。
おわりに
私の「主体」についての考え方は、自己理解、自己受容、自己表現を核とし、それらを胎・乳幼児期の経験(脳の記憶)、特に母親との関係性の中に深く根差しています。それは、個々人が持つ無限の可能性を信じ、生涯にわたる自己と人間観察・探求と成長を通じて、自己と他者、そして世界との調和を実現し、幸福と平和を創造するプロセスです。
この探求は終わりがなく、常に変化し、進化し続ける「未完成の旅」(楽しい不思議な世界の旅)であり、その旅路そのものが「主体を第1として生きる」ことの醍醐味なのです。
私たち一人ひとりが、この「主体」の探求を通じて、より豊かで幸福な人生を創造し、平和な社会の実現に向けて歩み続けることができる – そのことを心から願い、私自身も観察・探求を続けてまいります。