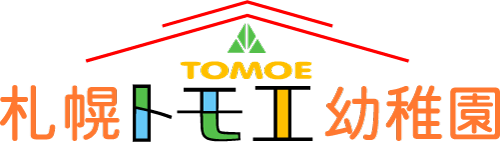特に母親の存在について
①命を育む存在
母親は、命を宿し育む存在として、人間社会の営みの中で特別な役割を担っています。胎児期から続く命の育みは、生命の神秘と不思議に満ち、その経験は母親自身に深い感受性と共感力を育てます。こうして培われた資質と、自らの存在への誇りは、日常のふるまいや人との関わりに自然に現れ、周囲に安心感と温もりをもたらします。母親は命のつながりや循環を象徴し、その姿は子どもだけでなく大人にも生命の尊さを思い起こさせます。コミュニティに母親がいることで、互いに思いやり、支え合う文化が芽生え、安心して暮らせる土壌が広がります。母親の存在は、次世代の健やかな成長を支えると同時に、命を尊重し合う温かなコミュニティづくりの中心的な柱となるのです。
②共感性
母親がトモエに参加する意義の一つは、胎児期から乳幼児期にかけて命を見守り、育む中で培われる深い共感性にあります。母親は、赤ちゃんの言葉にならない感情や欲求を敏感に感じ取り、寄り添い、応える日々を重ねることで、相手の「ありのまま」を受け入れる力や、微細な心の動きを察知する感性を自然と磨いていきます。また、乳幼児は大人の表情や声、接触のされ方に敏感で、母親はその反応に寄り添いながら共感的な関わりを学び続けます。こうした経験を持つ母親がコミュニティに加わることで、他の子どもや大人にも温かく共感的に関わる姿勢が広がり、互いを思いやる雰囲気が生まれます。その結果、コミュニティ全体が安心感と信頼に包まれ、子どもたちも大人も自分らしく過ごせる温かな場が育まれます。母親の共感性は、トモエのコミュニティをより豊かで調和のあるものにしていく大きな力となるのです。
③自己変容への柔軟さ
母親は子育てを通じて、子どもの成長や日々変化する要求に応える中で、柔軟に対応する力を培うことがあります。子どもは新しいことを学び、感じ方や考え方を変化させていくため、そのたびに母親は自分の考えや対応を見直し、時に戸惑いや悩みを抱えながらも変化を受け入れ、寄り添おうとします。こうした経験を重ねる中で、「変わること」や「新しい自分になること」に前向きになる傾向が育まれ、自分や他者の変化をしぜんに受け入れる姿勢が形づくられます。この柔軟さは、コミュニティにおいても価値ある力となり得ます。メンバーの変化や成長を喜び合い、互いに支え合う雰囲気を醸成することで、コミュニティ全体が温かく協調的な場へと育っていくのです。
④争いを避け、調和を選ぶ感性
母親は、妊娠・出産・子育てを通して、命を受け入れ、包み込み、調和を大切にしようとする姿勢を育む傾向にあります。この過程では、自分の限界や困難に向き合いながらも、子どもの成長や希望に応えるために感受性や共感力を発揮し、それらをさらに深めていく傾向もまた見られます。こうした経験は、生き方にも影響し、相手を受け入れ、協調して生きる方向へと導くことが少なくありません。こうした「争いを避け、調和を選ぶ感性」を持つ母親がコミュニティに加わると、他者への思いやりや信頼関係が広がり、対立よりも協調や調和を重んじる文化が育まれます。その結果、コミュニティは安心してつながれる場となり、人々の幸福やより平和な社会づくりへの貢献度が高まっていくのです。