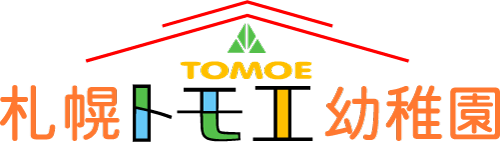素直な表現
①精神的安定~情緒の安定や自己肯定感、信頼、共感を育む土台
乳幼児は、泣く・笑う・怒るなど、感情や欲求をまっすぐに表します。これは気まぐれではなく、「おなかがすいた」「抱っこしてほしい」「わかってほしい」といった大切なサインです。まだ自分で生きていけないこの時期、子どもはこうした表現を通して大人と心をつなぎ、安心を得ようとします。もしその気持ちをあたたかく受け止めてもらえれば、「自分は大事にされている」「この世界は安全だ」という確かな感覚が心に育ちます。この感覚は、日々の情緒の安定(精神的安定)や自己肯定感、そして将来、人を信じたり、相手の気持ちに寄り添ったりする力の土台になります。乳幼児期に素直な表現をのびのびと出せる環境は、健やかな心の成長と精神的安定に欠かせない宝物なのです。
②自分や他者の素直な表現が、自己理解と他者理解を育む
乳幼児期に素直な表現ができることは、まず自分自身の気持ちや考えに気づき、それを言葉や行動で表す経験を積むことにつながります。自分の「好き」「嫌い」「うれしい」「悲しい」といった感情を素直に出すことで、「自分はこう感じているんだ」と自覚しやすくなり、自己理解が深まります。また、周囲の大人や友だちが本音を表現する姿に触れることで、「あの子はこう思っているんだ」「この人はこう感じているんだ」と、他者の気持ちや考えにも自然と関心が向きます。こうした体験を通して、子どもは自分と他者の違いや共通点に気づき、相手を理解しようとする気持ちが育ちます。自己理解と他者理解の両方が進むことで、子どもは自分の気持ちを大切にしながら、相手の気持ちにも寄り添えるようになり、豊かな人間関係を築く基礎が養われます。
③自己理解と他者理解のバランスの上に自己コントロールが可能になる
自己理解と他者理解が育つことで、初めて「自己コントロール」の力が芽生えます。これは感情や欲求を抑え込むことではなく、自分の気持ちを受け止めたうえで、状況や相手に応じて行動や表現を選べる力です。たとえば怒りや悲しみが湧いたとき、そのままぶつけるのではなく、「どうすればよいか」「相手はどう感じるか」を考え、気持ちを整理し、表し方を工夫します。この力があれば、集団生活や人間関係で協力し合い、トラブルを乗り越える経験が積めます。自己コントロールは単なる我慢ではなく、自分らしさを保ちながら他者と調和して生きるための柔軟な対応力なのです。
④受け入れ理解してくれる人への信頼感が増す~自分への信頼(自信)と他者への信頼
乳幼児が自分の気持ちや欲求を素直に表現し、それを大人が温かく受け止めてくれる経験は、心の成長にとってとても大切です。自分の思いを安心して伝えられることで、「自分は大切にされている」「わかってもらえる」という実感が生まれ、自己信頼(自信)が育ちます。また、大人に受け入れてもらうことで、「この人は信頼できる」と感じ、他者への信頼感も深まります。こうしたやりとりの積み重ねが、子どもが自分を肯定し、他者と良い関係を築く力の土台となります。乳幼児期に素直な表現を受け止めてもらうことは、将来の豊かな人間関係や社会性を育むうえで欠かせない経験です。
⑤自分を肯定しながら日々を過ごすことができる
乳幼児期において、子どもが自分の気持ちや欲求を素直に表現できる環境は、自己肯定感を育むうえで非常に重要です。大人がその表現を温かく受け止め、共感し、認めることで、子どもは「自分のままで愛されている」「無理に変わらなくていい」と感じることができます。こうした経験の積み重ねが、子ども自身の自信や自己信頼につながり、日々を前向きに過ごす力の土台となります。また、素直な表現が受け入れられることで、子どもは自分の感情や考えを否定せず、ありのままの自分を肯定しながら成長していくことができるのです。
⑥子どもの素直な表現が大人の子ども理解と人間理解を深める(大人にとっての意味)
周囲の大人が子どもの素直な表現に丁寧に向き合うことで、その子自身の個性や気持ち、考え方への理解が深まります。子どもが本音を出せる環境では、大人は「子どもとはこういう存在なのだ」と実感を持って受け止めることができ、表面的な行動だけでなく、その背景にある思いや成長の過程にも目を向けるようになります。こうした経験を重ねることで、大人自身の子ども観が広がり、ひいては「人間とは何か」という本質的な理解にもつながります。乳幼児の素直な表現を受け止めることは、子ども理解・人間理解の出発点となる大切な営みです。