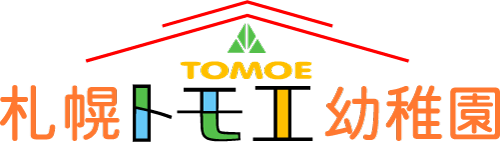自発的活動の重視
①主体性の保障 ~ 内発性、能動性
人間には、自分の内側から湧き上がってくる欲求があります。その一つの「遊びの欲求」は大人にもありますが、子どもは一日の多くの時間をその欲求の充足に当てます。そのために、子どもは自分で遊びを考え、それを実行します。その過程で、子どもは自分の主体性を発揮して能動的に活動します。多くの研究によって、子どもが周りの世界から自分の興味ある側面を切り取り、そこでの活動(遊び)に没頭するときに最もよく学ぶという結果が出ています。そしてそこには、自分で感じ考え、行動し、様々な問題を解決したり、新しい発見をしたりと、主体性を発揮することの心地よさ、充実感、満足感があります。それらは様々な学習や創造的な活動においても、また将来の社会人としての活動においても大きな意味を持つものです。
②充実感、満足感の保障 ~ 快、集中
人間にとって、日々の生活の中で充実感や満足感を得ることは、心の安定や幸福感につながる大切な要素です。自分の行動や存在が認められ、心から満たされる経験は、自己肯定感や自信を育みます。特に子どもにとっては、遊びがその役割を大きく担っています。子どもたちは自分の内から湧き上がるやりたい遊びを選び、夢中になって取り組むことで、しぜんと集中し没頭する時間を過ごします。その中で感じる楽しさや心地よさ(快)は、他人からの評価や見返りを求めるものではなく、純粋に「自分が自分でいられる」喜びです。こうした心から満たされる遊びの体験を通して、子どもたちは自己受容や自己信頼、自己有能感などを育むことができます。子どもの遊びにおいてこのような充実感や満足感が保障されることは、健やかな成長や幸せな毎日を送るためにとても重要なのです。
③必要性の保障 ~ 個性の尊重
子どもたちの遊びの欲求は一人ひとり異なり、その時々でさまざまな形で現れます。こうした違いは、胎児期から育まれてきた脳の神経細胞同士のつながりと、出生後の環境との相互作用によって生まれる「個性」として表れます。つまり、子どもたちが「これをしたい」「あれで遊びたい」と感じる気持ちは、その子自身の個性から生じる大切な必要性なのです。子どもが自分の内側から湧き上がる遊びの欲求を十分に満たすことは、その子の個性を認め、尊重することにつながります。そして、こうした必要性が保障されるのは、子どもたちが自発的に活動できる環境があるからこそです。子どもたちの遊びの必要性を大切にし、それを満たすことが、個性を尊重し、豊かな成長を支える基盤となります。
④関係性の保障 ~ 物との関係、人との関係
子どもは日々、友だちや大人、物や出来事など、さまざまなものと関わりながら生活しています。その中で、どの関係にどのように関わるかを自分で選ぶことができることは、とても大切です。たとえば、友だちの輪に入れなかったときは、一人で好きな遊びに集中して心を落ち着かせたり、誰かとけんかした後は、別の大人と遊んで気持ちを切り替えたりできます。また、歌や踊りなど自分の好きな活動を選ぶことで、気分転換や心のバランスをとることもできます。このように、その時々の自分の気持ちや状況に合わせて関係を選ぶことは、子どもが自分の心と向き合い、安心して過ごすための土台となります。自発的に関係を選ぶ経験は、子どもの心の健康や自己理解を深めるうえでとても重要です。
⑤自由の保障 ~ 自由と責任
人間には自己実現の自由があります。子どももまた、自分でやりたい遊びを選び、取り組むことでその自由を追求します。しかし、その過程で他者の自由とぶつかることがあり、そこで初めて「責任」という課題に向き合うことになります。自発的に行動した結果として生じる摩擦や葛藤は、自由と責任のバランスに悩む貴重な体験です。その体験こそが、子どもにとって大きな学びとなります。なぜなら、自分の行動が他者に与える影響を実感することで、思いやりや寛容、良心といった「やさしさ」や「道徳心」がしぜんに育まれていくからです。子どもたちは遊びの中で自分に課された課題を自ら受け止め、解決しようとする中で、他者と共に生きるための基盤を築いていくのです。
⑥時間の保障 ~ 自分時間
世界の時間は常に一定のリズムで進んでいます。しかし人間には、その流れとは別に、気持ちや状況によって長く感じたり短く感じたりする「主観的な時間感覚」があります。楽しいことに集中しているときは時間が早く過ぎ、退屈なときには時間がなかなか進まないように感じることがあります。多くの子どもは、こうした主観的な時間感覚に強く影響されながら日々を過ごしています。自分の興味から自発的に選んだ遊びに没頭する中で、子どもたちは自分のリズムで時間を使い、自分なりの世界をつくっています。そしてその体験を通して、自分の感じ方や関心を自由に表現しながら、社会の中で共有される客観的な時間とのつながりも少しずつ学んでいきます。こうした行き来の積み重ねが、社会的な時間の中で自分らしさを失わずに生きる力へとつながっていくのです。